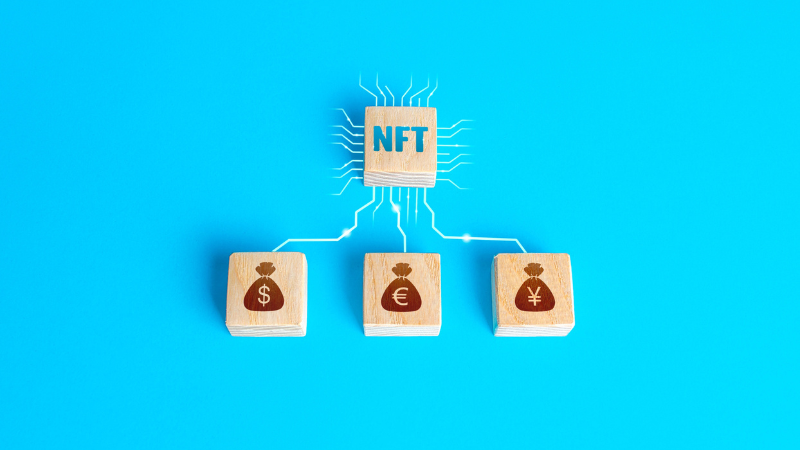有名な絵画や文化財が盗まれる。そんな映画のような話が実際に世界中で起きています。ゴッホやフェルメールの名画など歴史的価値の高い美術品が狙われた事件は少なくありません。この記事では国内外で起きた代表的な盗難事例を紹介しながら、美術品がなぜ狙われるのか、盗難後の行方、そして文化財保護の課題について解説します。
ムンク「叫び」盗難
ムンクの代表作「叫び」は世界的に知られる表現主義絵画であり、芸術的価値だけでなく象徴性の高さからも注目されています。そんな「叫び」は実際に2度の盗難被害に遭っています。1度目は1994年ノルウェーの冬季オリンピック開会式の日に発生しました。
「叫び」が盗まれた経緯
1994年2月12日、ノルウェー・リレハンメルで冬季オリンピックの開会式が行われた日でした。この日は世界中の注目がオリンピックに集まり、オスロ市内の警備が手薄になっていたことが犯行のタイミングとして狙われたとされています。
犯人は早朝にオスロ国立美術館へ侵入し、ハシゴとハンマーを使って窓を破壊。わずか50秒ほどで「叫び」を持ち去ったという極めて短時間の犯行でした。
盗難後の行方と奪還劇
この事件の主犯はパル・エンガーという人物です。彼は元プロサッカー選手で、ノルウェーのヴァーレンガというクラブに所属していました。エンガーは幼少期から「叫び」に強い執着を持ち、自分の人生と重なると感じていたそうです。
絵画は地下室に隠されていましたが、ロンドン警視庁の美術特捜班によるおとり捜査により発見されました。エンガーはノルウェー史上最長となる6年の実刑判決を受けました。
明日10/26の放送予定からピックアップ!★名画ムンクの「叫び」(油絵)が日本初上陸!盗難に遭った過去があるため、厳重な管理の中で準備する舞台裏にTVカメラ初潜入!さらに「叫び」にまつわる驚きのトリビアを紹介します。★ pic.twitter.com/YdQB3YTJ10
— 羽鳥慎一モーニングショー (@morningshow_tv) October 25, 2018
ダ・ヴィンチ「モナリザ」盗難
1911年、ルーヴル美術館でレオナルド・ダ・ヴィンチの代表作「モナリザ」が盗まれるという事件がありました。現在ではもっとも有名な絵画として知られていますが、事件当時、「モナリザ」はそれほど注目されておらず、事件が報道されることで初めて広く知られるようになりました。盗難をきっかけに世間の関心が高まり、「モナリザ」はやがて「伝説の絵画」として語られるようになりました。
「モナリザ」が盗まれた経緯
1911年8月21日、月曜日の朝。ルーヴル美術館は定休日で、館内は清掃やメンテナンス作業のみが行われていました。犯人ヴィンチェンツォ・ペルージャは作業服を着て職員になりすまし展示室から「モナリザ」を取り外し、服の中に絵を隠して堂々と持ち出しました。
盗難後の行方と奪還劇
ペルージャは窃盗の理由を、ナポレオンがイタリアから略奪した美術品を祖国に取り戻すためだと主張しました。彼は「モナリザ」がフランスにあることを不当だと考えていたのです。
「モナリザ」はペルージャの下宿先の床板の裏に2年間隠されていました。ペルージャはイタリアの美術商に対し「モナリザ」を売却したいと持ちかけ、作品を密かに持ち込みました。美術商は協力するふりをして絵画の鑑定を依頼し、結果的に本物であることが判明しました。その後、ペルージャは逮捕されました。ペルージャはイタリア国内で愛国者として一部で称賛され、裁判では1年と15日の懲役刑が言い渡されましたが、実際には数か月で釈放されています。
興味深いのは、事件発生直後にパブロ・ピカソも容疑者として一時逮捕されていたことです。ピカソは過去に盗品と思われる古代彫刻を購入していた経緯があり、捜査線上に浮上しましたが、後に無実が判明し釈放されています。
🗓️1911年8月21日、仏ルーヴル美術館からレオナルド・ダ・ヴィンチの『モナ・リザ』が盗まれる事件が発生。世界的なニュースとなり、美術館には「消えたモナリザ」を見ようと多くの人々が訪れるようになったという。#今日は何の日_Sputnik pic.twitter.com/0iw3dN5vfh
— Sputnik 日本 (@sputnik_jp) August 21, 2025
ゴッホ「春のヌエネンの牧師館の庭」盗難
フィンセント・ファン・ゴッホの初期作品「春のヌエネンの牧師館の庭」は1884年に制作された風景画で、彼が暮らしたヌエネンの牧師館の庭園を描いたものです。この作品は2020年、オランダの美術館から盗まれるという事件に巻き込まれました。新型コロナウイルスの影響で美術館が休館していたタイミングを狙った計画的な犯行でした。
「春のヌエネンの牧師館の庭」が盗まれた経緯
盗まれた「春のヌエネンの牧師館の庭」はフローニンゲン美術館から貸し出されていた作品で、オランダのシンガー・ラーレン美術館で特別展示されていました。2020年3月30日未明、犯人は美術館のガラス扉を破壊して侵入し、わずか数分でこの絵を持ち去りました。
盗難後の行方と奪還劇
事件後、絵画は長らく行方不明となっていましたが、2023年9月、オランダの美術探偵アーサー・ブランド氏のもとに匿名の人物から返還されました。絵画は青いIKEAバッグに入れられ、玄関先に届けられたという劇的な展開でした。
盗難のゴッホ作品、「美術界のインディ・ジョーンズ」が回収
— AFPBB News (@afpbbcom) September 13, 2023
盗難被害に遭っていたのは、1884年作の「春のヌエネンの牧師館の庭」で、推定価値は300万〜600万ユーロ(約4億7000万円〜9億4000万円)。オランダ警察が9月12日に発表した。 pic.twitter.com/AMCMbKwG5R
ロートレック「マルセル」盗難
フランスの画家アンリ・ド・トゥールーズ=ロートレックによる油彩画「マルセル」は1968年に京都国立近代美術館で開催されたロートレック展にて展示されていた作品です。展覧会の最終日、突如としてこの絵が姿を消すという前代未聞の盗難事件が発生しました。
「マルセル」が盗まれた経緯
1968年12月27日、展覧会の最終日。閉館後の館内でフランスから借り受けていた「マルセル」(当時の時価約3500万円)が突然と消えました。盗難から3日後、美術館から約200メートル離れた自転車置き場で額縁だけが発見され、現場には靴の跡が残されていました。
展示品には1億円以上の絵画がありましたが「マルセル」しか盗まれなかったことから換金目的ではなく熱狂的なファンによる犯行と推測されました。
盗難後の行方と奪還劇
捜査は難航し、犯人の特定には至らず、事件は未解決のまま公訴時効を迎えました。ところが1976年、大阪市に住む会社員の夫婦が「預かっていた絵がマルセルではないか」と新聞社に連絡しました。この絵は京都に住む中学校教諭から預かったものであり、夫婦は絵の中身については知らなかったと主張しています。鑑定の結果、絵は本物であることが判明し、フランスのトゥールーズ=ロートレック美術館へ返還されました。
1968年[マルセル盗難事件]が発生し大きな話題になりました。これは京都国立近代美術館で11月9日から開催されていたロートレック展の最終日に仏から借りて展示されていた油彩絵画のうちの一つマルセルが消えた事件で、結局犯人は分からぬまま1975年公訴時効が成立、1976年に発見され仏に返却されました pic.twitter.com/sHO5748v1q
— 懐かしくん (@Natsukashikun) April 8, 2024
盗難防止の取り組み
美術品盗難は単なる物理的損失にとどまらず、文化的・歴史的な喪失をも意味します。近年の事件を受けて、美術館や個人コレクター、国際機関はそれぞれ対策を強化していますが、依然として課題は残されています。
国際的な連携と法整備
インターポールによる盗難美術品データベースの運用
インターポール(国際刑事警察機構)は盗まれた絵画や文化財の情報を専用の国際データベースに登録し、加盟国の警察や美術館と連携しながら、作品の発見と返還につなげる活動を行っています。盗難美術品の画像・詳細・盗難状況などを世界中の捜査機関が共有できるようにすることで、国境を越えた追跡や摘発が可能になります。
ユネスコ条約による文化財返還の枠組み
ユネスコ条約は美術品や文化財の盗難・不正取引を防ぐための国際的な枠組みとして機能しています。ただし、「盗難を未然に防ぐ」よりも「盗まれた後の流通を止め返還を促す」ことに重点が置かれています。
国内の法制度と取り組み
古物営業法は美術品などの中古品を扱う業者(古物商)に対して売主の本人確認や取引記録の保存を義務づける法律です。盗まれた美術品が市場に出回ったとき、古物商がこの法律に基づいて適切に対応していれば、流通経路を追跡し、発見・返還につながる可能性が高まります。
まとめ|盗まれた美術品が語るもの
美術品盗難は単なる犯罪行為ではなく、文化・歴史・人間の欲望が交差する複雑な現象です。世界的な名画が実際に盗まれ、回収・修復・再展示までに長い時間と多くの人の努力が必要でした。
現在では美術館や個人コレクターによる警備体制の強化、国際的な法整備、盗難品のデータベース化など、保護の仕組みは進化しています。しかし行方不明のままの作品も多く、盗難防止と文化財保護の課題は今も続いています。
美術品盗難は文化の継承を脅かす重大な犯罪です。こうした事件を通じて私たちは美術品を守る責任と、その価値を改めて考える必要があります。