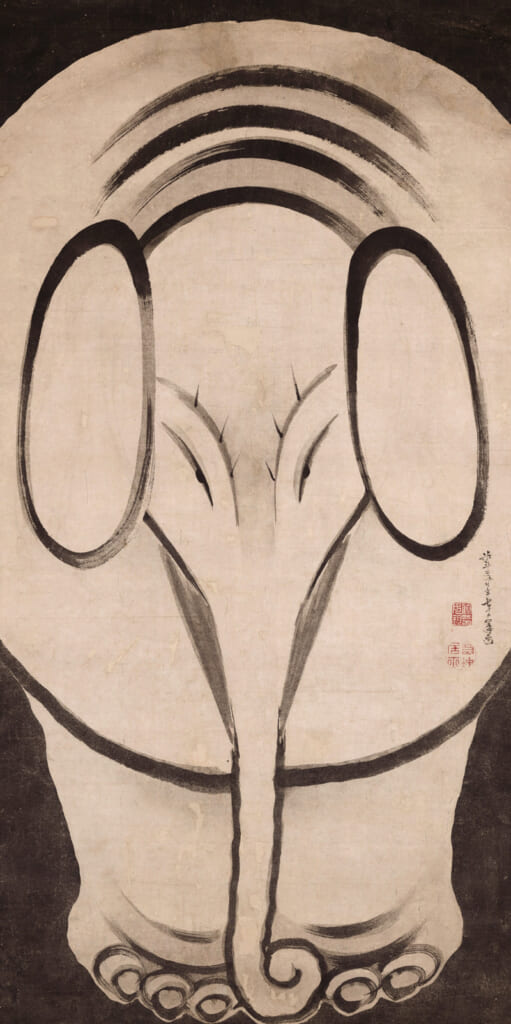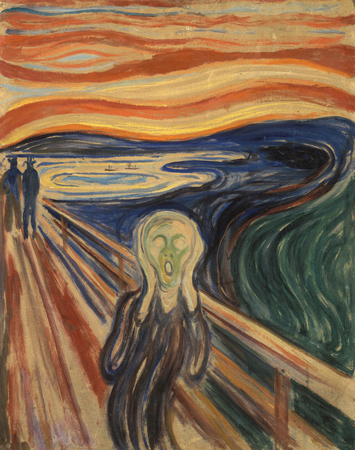名画「オフィーリア」はジョン・エヴァレット・ミレーが19世紀に描いたラファエル前派の代表作として知られています。シェイクスピア『ハムレット』の悲劇的ヒロインを題材に、水面に浮かぶ女性の姿を静謐かつ鮮烈に描いたこの作品の裏にあるエピソードを解説します。
ジョン・エヴァレット・ミレーとは
ジョン・エヴァレット・ミレー(1829–1896)はイギリスの画家であり、ラファエル前派のメンバーとして知られます。11歳でロイヤル・アカデミー付属美術学校に最年少で入学し、若くして才能を認められました。1848年、ウィリアム・ホルマン・ハントやロセッティとともにラファエル前派を結成し、自然描写と細密な表現を重視した革新的な絵画スタイルを展開しました。また肖像画家としても成功し、著名人の肖像を多く手がけました。
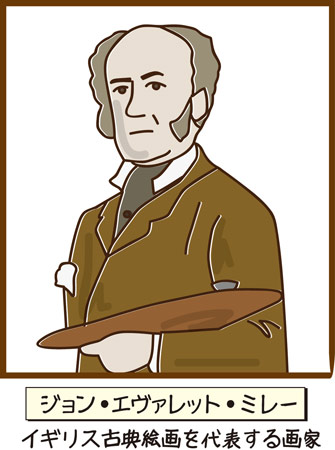
■ジョン・エヴァレット・ミレーの特徴
ラファエル前派の創設者
ミレーは1848年にウィリアム・ホルマン・ハント、ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティとともに「ラファエル前派」を結成しました。彼らはルネサンス以降のアカデミックな絵画様式(特にラファエロ以降の様式)に反発し、自然への忠実さ、細密描写、象徴性、道徳的主題を重視した新しい芸術を目指しました。
自然描写の精密さ
ミレーの作品は草木、水面、衣服の質感など、自然の細部を徹底的に観察して描くことに特徴があります。代表作「オフィーリア」では川辺の植物や水の流れが非常に緻密に描かれています。
感情表現と物語性
ミレーは人物の表情やポーズを通して物語性や心理描写を強く打ち出すスタイルを確立しました。悲劇的な場面や日常の情景に、静かな感情の深みを込めることが得意でした。
「オフィーリア」にまつわるエピソード
ジョン・エヴァレット・ミレーの「オフィーリア」は、シェイクスピアの戯曲『ハムレット』第4幕第7場の一場面を視覚化した作品です。オフィーリアが精神を病み川に落ちて命を落とす直前またはその瞬間を自然描写と象徴を駆使して描きました。

ジョン・エヴァレット・ミレー 「オフィーリア」 (1851)
その1:モデルはエリザベス・シダル
「オフィーリア」に描かれている女性は、実在の人物エリザベス・シダルをモデルにしています。彼女は19世紀イギリスのラファエル前派の芸術運動に深く関わった女性で、多くの作品のモデルとして活躍しました。
その2:モデルの父親が治療費を請求
ミレーはオフィーリアが川に浮かびながら死に至る場面をリアルに描くため、シダルをアトリエの浴槽に浮かべて長時間ポーズを取らせました。寒い冬の日、石油ランプで湯を温めていたものの途中で火が消えてしまい、シダルは肺炎寸前まで風邪をこじらせてしまいます。シダルの父親はミレーに激怒し、治療費を請求されたといわれています。
その3:花言葉がちりばめられている
ヴィクトリア朝の人々は、言葉にしにくい感情やメッセージを花の象徴に託して伝える文化を持っていました。ミレーはこの文化を巧みに取り入れ、オフィーリアの悲劇を視覚的に語る手段として花々を配置しています。ケシ=死、ひな菊=無垢、パンジー=空しい愛など、オフィーリアの運命を暗示する要素がちりばめられています。
その4:実際の風景を5か月かけて描いた
背景の川辺はロンドン郊外サリー州のホグズミル川。ミレーは約5カ月をかけて現地で風景を描写し、自然への忠実さを追求しました。現在ホグズミル川の場所には記念板が設置されており、訪れる人々がその風景を体感できるようになっています。
その5:夏目漱石の作品にも登場
文豪・夏目漱石は小説『草枕』(1906年)の作中では、水辺に佇む女性や自然と融合するような描写が繰り返し登場し、「オフィーリア」を想起させる場面が随所に見られます。夏目漱石が『草枕』を執筆する数年前、彼はロンドン留学中にナショナル・ギャラリーでミレーの「オフィーリア」を鑑賞し、川に浮かぶ女性の静謐な姿は言葉にならない癒しと衝撃を与えたとされています。
「オフィーリア」が語る、絵画の奥深さ
ジョン・エヴァレット・ミレーの「オフィーリア」はラファエル前派の理念を体現しながら、視覚的な物語性と感情表現を追求し、今なお多くの人々の関心を集めています。「オフィーリア」は、絵画が語る力と、その裏にある人間ドラマの両方を感じ取れる名画の一つです。